「売上を伸ばしたい」「営業リソースが足りない」「採用が間に合わない」――このような課題を抱える企業にとって、営業代行は非常に有効な解決策となり得ます。
しかし、「どの営業代行会社を選べばいいのかわからない」「高額な費用を払ったのに成果が出なかったらどうしよう」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、10年以上の営業経験を持ち、自身も顧客として複数回営業代行を選定してきた私が、その経験と知識に基づき、失敗しない営業代行の選び方を徹底解説しますので、最後までご覧ください。
そもそも営業代行とは?基礎知識と知っておくべきこと
営業代行会社を選ぶ前に、まずは基本的な知識を押さえておきましょう。
営業支援と営業代行の違い
混同されがちですが、「営業支援」と「営業代行」には明確な違いがあります。
- 営業支援:営業戦略の立案、施策の検討、実行プロセスのサポートなど、「戦略・企画」から「実行」まで幅広く支援します。
- 営業代行:主にアポイント獲得や商談実行など、「実行リソース」の提供に特化しています。
近年では、両方を一貫して提供する企業も増えています。自社の課題が戦略レベルにあるのか、それとも実行リソース不足なのかを明確にすることで、適切なサービスを選びやすくなります。
「丸投げ」は可能?
結論から言うと、本当の意味での「丸投げ」は不可能だと考えてください。営業代行会社はあくまでパートナーであり、最大のパフォーマンスを引き出すためには、自社側でも一定の管理工数が発生します。
例えば、週に1回以上の定例を設定し、進捗状況の確認やフィードバック、PDCAサイクルを高速で回すことで、よりスピーディーな成果創出が期待できます。
営業代行の報酬体系:メリット・デメリットを徹底比較
営業代行の報酬体系は、大きく以下の3種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自社の予算や目的に合ったものを選びましょう。
1. 固定報酬型
毎月一定の固定費用が発生するタイプです。 例:月額35万円で月間1,000件の架電を実施
- メリット:約束された稼働量(架電数や訪問数など)が担保されるため、活動量が安定します。
- デメリット:成果が約束されないため、費用を支払っても期待する成果が得られない可能性があります。稼働量を満たせば契約が成立するため、成果へのインセンティブが働きにくい場合があります。
2. 成果報酬型
アポイント獲得や受注など、成果に応じて報酬が発生するタイプです。 例:アポイント獲得1件につき3万円、受注1件につき15万円
- メリット:成果が出ない限り費用が発生しないため、リスクを最小限に抑えられます。
- デメリット:稼働量が保証されないため、他案件の兼ね合いで自社サービスへの稼働が後回しになったり、質より量を重視した「とにかくアポを取る」という行動に走りやすい傾向があります。結果として、質の低いアポイントが増える可能性があります。
3. 複合型
固定報酬と成果報酬を組み合わせたタイプです。 例:10万円の固定報酬+アポイント獲得1件につき2万円
- メリット:固定報酬を抑えつつ一定の稼働量を確保でき、成果が出れば追加で報酬を支払う形となるため、双方にとってバランスの取れた形になりやすいです。
- デメリット:アポイント獲得が容易な案件でないと引き受けてもらえなかったり、固定報酬が低い分、プロフェッショナルではない人材(アルバイトや学生など)がアサインされるリスクもあります。営業代行会社側は、固定報酬で最低限の時給を確保しつつ、アポ獲得で追加利益を得るインセンティブが働くため、アサインされる人材の質には注意が必要です。
営業代行の費用相場:大手からフリーランスまで
営業代行の費用は、依頼先によって大きく異なります。
大手・知名度のある営業代行会社
Web検索で上位表示されるような企業は、マーケティングに力を入れている証拠でもありますが、その分費用も高額になる傾向があります。 1人あたりの稼働で月額60万円以上が相場です。 例:セレブリックス(初期費用80万円~+月額90万円~)、BALES(80万円~)、セイヤク(60万円~)、SORAプロジェクト(60万円~)など。
中小の営業代行会社
Web検索上位には出てこないものの、質の高いサービスを提供する中小企業も多数存在します。 1人あたりの稼働で月額30万円~程度の会社もあります。 「カクトク」のような営業マッチングプラットフォームを活用すると、自社に合った中小企業を見つけやすいでしょう。
営業フリーランス
営業経験10年以上のベテランから経験の浅い方まで、幅広い人材がいます。 法人に依頼するよりも安価な費用で依頼できる可能性がありますが、人材を見極める力が重要になります。質の高いフリーランスを見つけることができれば、費用対効果は非常に高くなるでしょう。
【元選定者が語る】失敗しない営業代行の選び方5つのポイント
ここからが本題です。私が営業代行を選定する際に最も重視してきた5つのポイントをご紹介します。
1. 自社の事業フェーズと目的、求める支援範囲を明確にする
まずは、自社がどのような状況にあり、営業代行に何を期待するのかを明確にすることが最も重要です。
- 例1:自社で勝ちパターンがあり、採用が追いつかず実行リソースが欲しい場合
- 戦略や施策は自社で担い、実行リソースとしての営業代行(アポイント獲得や商談代行)に特化して外部委託するのが効率的です。
- 例2:まだ売上実績がなく、勝ちパターンが定まっていない場合
- 実行リソースだけでなく、戦略立案から実行まで一貫して支援してくれる営業支援会社を選ぶ方が、より根本的な課題解決に繋がりやすいでしょう。
自社の事業フェーズと目的に合わせて、最適な支援範囲を見極めましょう。
2. 「誰が」架電・営業するのかを徹底確認する
会社の規模や実績、知名度よりも、実際に「誰が」架電・営業するのかが、成果に最も直結すると断言できます。
- たとえ有名企業でも、実際に現場で動くのが経験の浅いアルバイトやインターン生では、期待する成果は得にくいでしょう。
- 特に、知名度の低いサービスで新規開拓(アウトバウンドコール)を行う場合、その難易度は非常に高くなります。成果を期待するなら、やはりプロフェッショナルな人材のアサインが不可欠です。
プロジェクトマネージャー(PM)が優秀でも、現場のメンバーの質が低ければ、期待通りの成果は望めません。育成には時間がかかるため、すぐに成果を求める場合はミスマッチのリスクが高まります。
チェック項目:実際に営業を担当するメンバーの質を見極める
- 営業経験年数:最低でも3年以上の営業経験がある方が望ましいです。経験が長ければ長いほど、質の高い営業活動が期待できます。営業代行会社の採用力や定着率の高さも判断基準になります。
- 過去の類似案件・類似企業での実績:自社の商材やターゲット、企業の規模感(大手・中小・ベンチャーなど)と類似した案件での実績があるかを確認しましょう。大手企業での実績があっても、ベンチャー企業の営業とは勝手が違う場合があります。
- 音源や会話の雰囲気:可能であれば、実際に架電予定者の音源を聞かせてもらったり、事前に話す機会を設けたりして、コミュニケーション能力や経験レベルを確認しましょう。
3. 組織のマネジメント体制、育成体制を確認する
「誰が」営業するかに加えて、そのメンバーを「どのように」マネジメント・育成しているかも非常に重要です。
- プロジェクト統括者の経歴:プロジェクトマネージャー(PM)の営業経験が浅い場合、適切な指示やフィードバックが期待できない可能性があります。PMの経験や実績を確認しましょう。
- 組織的なマネジメント体制:PM1人に対しメンバーが多数いるような体制で、PMがすべてのメンバーを細かく管理できているか。定期的なフィードバックや進捗共有の仕組みが整っているかを確認しましょう。
- 中長期的なメンバー育成の仕組み:具体的にどのような研修を実施しているのか、週にどれくらいの時間をかけてフィードバックを行っているのかなど、具体的かつ継続的な育成への取り組みが見られる企業を選びましょう。会社として質の担保にどれだけ真剣に取り組んでいるかが見えてきます。
4. 類似案件の実績と費用対効果のシミュレーションを行う
上記の1~3で「成果創出の期待が持てそう」と感じたら、次に具体的な実績と費用対効果をシミュレーションしてみましょう。
- 類似案件の実績確認:
- 架電数、アポイント獲得数、アポイント率
- 受注数、受注率
- これらの数値が、自社の商材やターゲットと類似した案件でどの程度だったのかを確認します。
- 費用対効果のシミュレーション:
- 自社の商談からの受注率や、1件あたりの受注単価・利益を明確にします。
- 営業代行会社が提示する実績データと、自社のデータを掛け合わせ、「投資した費用に対してどれくらいの利益が見込めるのか」を具体的に計算してみましょう。
- 例えば、月額50万円で月間1,000件の架電、アポ率1%、自社の商談からの受注率10%、1件受注で100万円の利益の場合…
- 1,000件架電 × 1% (アポ率) = 10件アポイント獲得
- 10件アポイント獲得 × 10% (受注率) = 1件受注
- 1件受注 = 100万円の利益
- この場合、月額50万円の費用で100万円の利益が見込めるため、費用対効果は高いと言えます。(自社の商談担当の人件費なども考慮に入れると、より精度の高いシミュレーションが可能です。)
具体的な数値でシミュレーションすることで、より明確な成果イメージを持つことができます。
5. 契約期間と解約条件を必ず確認する
契約期間が長期にわたる場合や、中途解約に高額な違約金が発生するケースもあるため、契約内容の確認は非常に重要です。
- 契約期間:
- 自信のある営業代行会社であれば、まずは1ヶ月や3ヶ月といった短期契約に応じてくれることもあります。
- 成果が出るまでに時間がかかるケースもありますが、サービスの性質上、実際に活用してみないと質が見えない中で、いきなり年間契約を迫る企業には注意が必要です。
- 解約条件:
- 万が一、期待する成果が得られなかった場合に、どのような条件で解約できるのか、違約金は発生するのかなど、解約に関する条項を細部まで確認しましょう。
営業代行会社への質問リスト10選
私が営業代行会社を選定する際に実際に確認していた質問項目をまとめました。これらの質問をすることで、より深く相手企業を理解し、成果創出のイメージを具体化することができます。
- 他社との違いや、御社の強み・特徴は何ですか?
- 実際に架電・営業を担当するメンバーは、どのような方がアサインされますか?(営業経験年数、過去の実績など)
- 組織のマネジメント体制、メンバーの育成体制はどのようになっていますか?(具体的な取り組み内容)
- 全体の架電数、アポイント獲得数、アポイント率、受注数、受注率の実績を教えてください。
- 弊社と類似する商材やターゲットでの、過去の類似案件の実績(架電数、アポイント獲得数、アポイント率、受注数、受注率)を教えてください。
- 弊社をご支援いただいた場合、どのような成果が見込めるとお考えですか?(具体的なシミュレーションがあれば)
- 弊社が最大の成果を出すために、事前に準備すべきことや、協力すべきことは何だと感じていますか?
- 契約期間の選択肢と、それぞれの契約期間におけるメリット・デメリットを教えてください。
- 費用体系(固定報酬、成果報酬、複合型)と、それぞれの費用詳細について説明してください。
- 稼働開始はいつ頃から可能ですか?
まとめ:最適な営業代行を選び、事業を加速させよう
営業代行の選定は、自社の事業成長を左右する重要な決断です。しかし、そもそも営業代行が本当にあなたの会社の課題解決に最適な手段なのかを、まず最初に確認することが何よりも重要です。自社の現状と課題を深く分析し、その上で営業代行が有効な選択肢であると判断できたなら、本記事でご紹介した5つのポイントを参考に、自社に最適なパートナーを見つけてください。
- 自社の事業フェーズと目的、求める支援範囲を明確にする
- 「誰が」架電・営業するのかを徹底確認する
- 組織のマネジメント体制、育成体制を確認する
- 類似案件の実績と費用対効果のシミュレーションを行う
- 契約期間と解約条件を必ず確認する
これらのポイントを押さえることで、費用対効果の高い営業代行会社と出会い、貴社の売上拡大に貢献してくれるでしょう。
営業に悩んでいるのであれば、以下の記事もおすすめです。
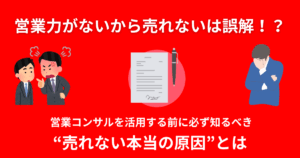
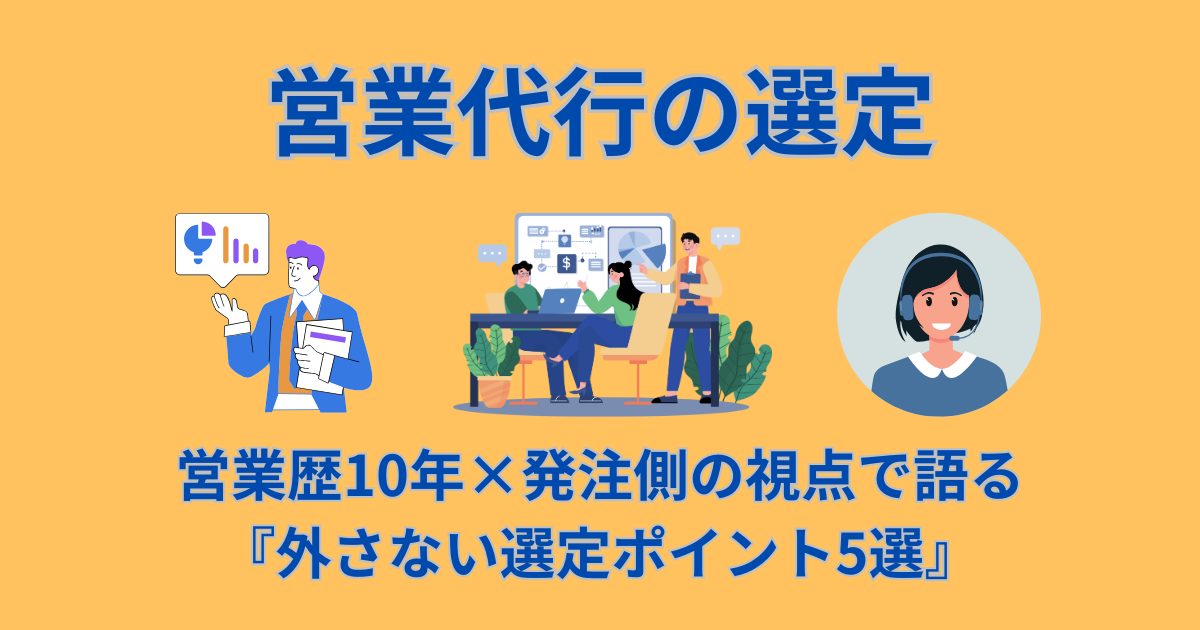

コメント