「フルリモート勤務って憧れるけど、本当に自分に合うのかな?」
毎日の通勤から解放され、好きな場所で働けるフルリモートは魅力的ですよね。しかし、その一方で「会社への帰属意識が薄れる」「オン・オフの切り替えが難しい」といったデメリットがあることも事実です。
私自身、フルリモートで働き始めてから今年で5年目になります。初めはメリットばかりに目を向けていましたが、実際に体験してみると、想像していなかった苦労や課題に直面しました。
本記事では、フルリモート5年目の私が実際に経験した、代表的なデメリット5つをデメリットが生じる理由から具体的な事例、解決策まで詳しく解説していきます。また、どんな人がフルリモートに向いているのか、デメリットを大きく上回るメリットは何かをお伝えしますので、最後までご覧ください。
フルリモートとは
フルリモートとは、出社せずにすべての業務を自宅や好きな場所から行う働き方のことです。
「リモートワーク」や「テレワーク」と呼ばれることもあり、オフィスに出社する回数が週に数回ある「ハイブリッド勤務」とは区別されます。
パソコンとインターネット環境さえあれば、どこでも仕事ができるため、働き方の多様化が進む現代において注目されています。しかし、その自由度の高さゆえに、知っておくべきデメリットも存在します。
デメリット1: 会社への帰属意識が薄まり、一体感を得にくい
フルリモート勤務の最大のデメリットの一つが、会社やチームへの帰属意識が薄れてしまうことです。
デメリットが生じる理由
オフィスで働いていると、同僚と顔を合わせ、ちょっとした雑談を交わしたり、ランチを一緒に食べたりする中で、自然と一体感が生まれます。
しかし、フルリモートでは物理的な距離があるため、そのような偶発的なコミュニケーションがほとんどなくなります。
仕事の会話はチャットツールやオンライン会議ツールが中心となり、どうしても形式的になりがちです。
結果として、自分の仕事が会社の目標にどう貢献しているのかが見えにくくなり、「自分は会社の歯車の一部にすぎないのでは」という疎外感を抱いてしまうことがあります。
特に、チームで何かを成し遂げたときの達成感や高揚感を直接共有する機会が減るため、モチベーションの維持が難しくなることも少なくありません。
事例
あるIT企業のエンジニアAさんは、フルリモートで働き始めた当初は通勤がないことに喜びを感じていました。
しかし、数ヶ月が経つと「自分の仕事は本当に会社の役に立っているのだろうか?」と漠然とした不安を抱くようになりました。
プロジェクトの進捗はチャットで共有されるものの、同僚がどのように奮闘しているのか、どんな課題に直面しているのかが分からず、一体感を感じることができませんでした。
忘年会や社員旅行などの社内イベントもオンライン開催となり、以前のような盛り上がりを感じられず、気づけば会社への関心が薄れていったそうです。
これは私自身もフルリモートを始めたばかりの頃に感じていたことです。仕事は問題なく進んでいるのに、ふと孤独感に襲われ、「自分は会社に必要とされているのだろうか?」と悩んだ時期もありました。
対策
帰属意識を保つためには、自ら積極的にコミュニケーションを取る姿勢が重要です。
例えば、以下のような対策が考えられます。
- 雑談専用のオンラインチャンネルを活用する:
業務とは関係のない雑談や趣味の話題を話せるチャンネルを作り、積極的に参加してみましょう。 - 1on1ミーティングを定期的に設定する:
上司やチームメンバーと定期的に1対1のオンラインミーティングを設定し、仕事の進捗だけでなく、キャリアの悩みやプライベートな話も共有する機会を設けるのが効果的です。 - ランチや飲み会をオンラインで開催する:
チームメンバーと一緒に食事をしながらオンラインで話す機会を作ることで、顔と顔を合わせて話す時間を作りましょう。
デメリット2: 直接指導してもらう機会が減る
若手ビジネスマンや、新しい分野に挑戦する人にとって大きなデメリットとなるのが、上司や先輩から直接指導してもらう機会が減ることです。
デメリットが生じる理由
オフィス勤務では、仕事で困ったとき、すぐに上司や先輩に声をかけて質問したり、相談したりできます。
隣の席の先輩の仕事ぶりを間近で見て学んだり、会議での発言や顧客とのやり取りを直接聞いたりすることで、多くのことを吸収できます。
しかし、フルリモートでは、質問をするにもチャットで文章をまとめる必要があり、ニュアンスが伝わりにくかったり、返信を待つ時間が発生したりと、リアルタイムなやり取りが難しくなります。
また、上司も部下の状況をリアルタイムで把握することが難しくなり、適切なタイミングでフォローや指導を行うのが困難になります。
結果として、OJT(On the Job Training)が機能しにくくなり、成長のスピードが鈍化してしまう可能性があります。
事例
入社2年目のBさんは、新しいプロジェクトの担当になりました。しかし、フルリモートのため、上司に質問するタイミングが掴めず、一人で悩む時間が増えてしまいました。
チャットで質問しても、意図がうまく伝わらず、何度もやり取りを繰り返すうちに「こんな簡単なことを何度も聞いてはいけないのでは?」と萎縮してしまい、質問すること自体をためらうようになりました。
その結果、ミスを連発してしまい、上司から「もっと報連相を徹底してほしい」と注意されることに。本来、オフィスで直接話していればすぐに解決できたであろう問題が、コミュニケーションの障壁によって複雑化してしまったのです。
対策
直接指導の機会を補うためには、受け身ではなく、自ら学びの機会を創出することが大切です。
- 報連相のルールを明確にする:
「何か困ったことがあったら、すぐにオンラインで声をかけてもいいですか?」など、上司と報連相のルールを事前に決めておくと安心です。 - チャットではなくオンライン会議で質問する:
複雑な質問や相談は、チャットではなくオンライン会議を設定して、画面共有しながら直接話すようにしましょう。 - 定期的な進捗報告の場を設ける:
毎日5分でもいいので、上司とオンラインで進捗を共有する時間を設けることで、困っていることがあれば早期に相談できる環境を作ります。
デメリット3: 仕事とプライベートのオン、オフがつけにくい
フルリモート勤務は、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりやすいという大きなデメリットがあります。
デメリットが生じる理由
オフィス勤務では、会社に着いたら仕事モードに切り替え、退社すればプライベートモードになるのが一般的です。通勤という物理的な移動が、気持ちのオン・オフを切り替える役割を果たしてくれます。
しかし、フルリモートでは自宅が仕事場となるため、物理的な区切りがありません。
朝起きてすぐに仕事を始められ、仕事が終わった後もすぐにプライベートに戻れるというメリットがある反面、「ついダラダラと仕事をしてしまう」「仕事が終わった後も、パソコンが気になってしまう」といった状況に陥りやすいのです。
また、家族が在宅している場合、仕事中に話しかけられたり、家事育児に気を取られたりして、仕事に集中できないこともあります。
結果として、長時間労働につながったり、精神的なストレスを抱えやすくなったりする可能性があります。
事例
広告代理店に勤めるCさんは、フルリモートで働き始めてから、終業時間になってもなかなか仕事をやめられなくなってしまいました。
オフィスにいるときは、周囲の人が帰宅するのを見て自分も帰る時間だと判断できましたが、自宅では誰にも邪魔されることなく仕事ができてしまうため、気づけば夜遅くまで作業を続けてしまうことが増えました。
また、休日も仕事のメールやチャットが気になり、ついつい確認してしまう癖がつき、常に仕事のことを考えてしまい、完全にリフレッシュすることができなくなってしまいました。
私自身もフルリモートを始めたばかりの頃は、朝起きてパジャマのまま仕事を始め、気づけば残業していた、という生活を続けていました。仕事とプライベートの区別がつかなくなり、いつの間にか疲労が蓄積してしまった経験があります。
対策
オン・オフの切り替えをうまく行うためには、自分なりのルールを設けることが大切です。
- 仕事部屋や仕事スペースを確保する:
可能であれば、仕事専用の部屋やスペースを設け、仕事が終わったらその場所から離れるようにしましょう。 - 就業時間と終業時間を明確にする:
「朝9時に仕事を始め、夕方6時にはパソコンを閉じる」といったように、働く時間をきっちり決めて守ることが重要です。 - オフの時間を意識的に設ける:
仕事が終わったらすぐに着替えたり、散歩に出かけたりするなど、「仕事モード」から「プライベートモード」へ切り替えるための行動を意識的に取り入れることで、精神的なオン・オフをつけやすくなります。
デメリット4: 運動不足になりやすい
フルリモート勤務では、圧倒的に運動量が減り、運動不足に陥りやすいというデメリットがあります。
デメリットが生じる理由
オフィス勤務では、毎日の通勤だけでもかなりの運動量になります。また、オフィス内を移動したり、ランチに出かけたりと、仕事中に体を動かす機会が自然とあります。
しかし、フルリモートでは、ベッドから起きてパソコンの前に座り、一日中その場から動かないという生活になりがちです。
結果として、肩こりや腰痛、眼精疲労などの身体的な不調を引き起こすだけでなく、肥満や生活習慣病のリスクを高めることにもつながります。
さらに、運動不足は精神的な不調にもつながることが指摘されており、ストレス解消の機会を失ってしまうことも大きな問題です。
事例
営業職のDさんは、フルリモートになる前は外回りが多かったため、毎日1万歩以上歩いていました。
しかし、フルリモートに切り替わってからは、会議も商談もすべてオンラインになったため、外出する機会が激減しました。
気づけば一日の歩数は数百歩という日も多くなり、肩こりや腰痛に悩まされるようになりました。
また、体を動かさないことで気分が落ち込む日が増え、「最近、なんだかやる気が出ないな」と感じることが多くなったそうです。
対策
運動不足を解消するためには、意識的に体を動かす習慣をつくることが不可欠です。
- 定期的に休憩時間を設ける:
1時間に1回は立ち上がってストレッチをする、窓を開けて深呼吸をするなど、体を動かす時間を確保しましょう。 - 積極的に外出する機会を作る:
ランチは外に食べに行く、仕事の合間に近所を散歩するなど、意図的に外に出る時間を作りましょう。 - 通勤時間を活用する:
「もし通勤していたら、これくらいの時間を使っていただろう」と想定して、その時間を運動に充てるのも効果的です。たとえば、仕事前や仕事後にジムに行く、ランニングをする、といった習慣を取り入れるのも良いでしょう。
デメリット5: 人と交流したい欲が高まる
フルリモート勤務が続くと、人間関係が希薄になり、孤独を感じやすくなるというデメリットがあります。
デメリットが生じる理由
人は社会的な生き物であり、他者との交流を通じて精神的な安定を得たり、モチベーションを保ったりしています。
オフィス勤務では、同僚との雑談やランチ、仕事帰りの一杯など、自然と他者と交流する機会があります。これらの交流は、仕事のストレスを和らげたり、新しいアイデアが生まれたりするきっかけにもなります。
しかし、フルリモートでは、仕事のコミュニケーションが主となり、それ以外の非公式な交流がほとんどなくなります。
一人で黙々と仕事をする時間が長くなるため、「誰とも話していないな…」と孤独を感じるようになり、結果として精神的なバランスを崩してしまう人も少なくありません。
事例
企画職のEさんは、元々人と話すのが好きなタイプでした。しかし、フルリモートになってからは、チームメンバーとの会話は業務連絡が中心となり、雑談する機会が激減しました。
仕事が終わっても、誰とも話すことなく一日が終わってしまう日が多くなり、週末には「誰かと会って話したい」という気持ちが強くなりました。
次第に、仕事へのやりがいよりも、人間関係への不満が募るようになり、気分が落ち込むことが増えたそうです。
私もフルリモートに切り替わって最初の1年間は、孤独感に悩まされました。社外の友人と会う機会を意識的に増やしたり、趣味のコミュニティに参加したりして、ようやくバランスが取れるようになりました。
対策
孤独感を解消するためには、意識的に人とのつながりを作る努力が必要です。
- オンラインの雑談会に参加する:
会社によっては、オンラインでのランチ会や雑談会を設けているところもあります。積極的に参加してみましょう。 - 社外のコミュニティに参加する:
趣味のサークルや地域のイベントに参加するなど、社外で新しい人間関係を築くことで、孤独感を和らげることができます。 - 友人や家族との時間を大切にする:
仕事が終わった後、オンラインで友人と話す時間を設けたり、家族と過ごす時間を増やしたりすることも効果的です。
フルリモート勤務は避けた方がいい人
ここまでフルリモート勤務のデメリットを見てきましたが、これらのデメリットは、特定のタイプの人にとっては致命的になる可能性があります。
ここでは、フルリモート勤務を避けた方がいい人の特徴をいくつか紹介します。
社会人歴が浅い人(目安3年以内)
社会人歴が浅い時期は、仕事の進め方やビジネスマナー、専門的な知識などを、先輩や上司の仕事ぶりを間近で見て学ぶことが非常に重要です。
フルリモートでは、そうした偶発的な学びの機会が減るため、成長のスピードが遅くなる可能性があります。
もちろん、フルリモートで成長している人もいますが、自ら積極的に質問したり、学んだりする姿勢がなければ、周囲との差が開きやすくなってしまいます。
未経験領域の転職
新しい業界や職種に転職する際は、多くのことを学ぶ必要があります。
未経験の領域では、想定外のトラブルや不明点が多く発生するため、すぐに質問できる環境が不可欠です。
フルリモートでは、質問のハードルが高くなりがちで、一人で抱え込んでしまうリスクがあるため、未経験からの転職にはハイブリッド勤務など、出社を伴う働き方がおすすめです。
セルフマネジメント能力が低い人
フルリモート勤務は、自分で時間やタスクを管理する能力が求められます。
「言われたことしかやらない」「タスクの優先順位がつけられない」「自己管理が苦手」というタイプの人は、仕事の進捗が滞ったり、勤務時間中にサボってしまったりするリスクがあります。
誰にも監視されていない状況でも、自律的に行動できる人でないと、フルリモートは厳しい働き方だと言えるでしょう。
テキストコミュニケーション能力が低い人
フルリモートでは、チャットやメールが主要なコミュニケーション手段となります。
そのため、文章だけで自分の意図を正確に伝えたり、相手の意図を汲み取ったりする能力が非常に重要です。
「文章で説明するのが苦手」「相手の気持ちを察するのが苦手」というタイプの人は、コミュニケーションの齟齬が生まれやすく、人間関係のトラブルにつながる可能性があります。
ITスキルが著しく低い人
フルリモートでは、オンライン会議ツールやチャットツール、ファイル共有ツールなど、様々なITツールを使いこなす必要があります。
「パソコンの操作が苦手」「新しいツールを覚えるのが億劫」という人は、仕事の効率が著しく低下したり、業務に支障をきたしたりする可能性があります。
基本的なITスキルは、フルリモートで働く上での前提条件となります。
フルリモートで成果を出すためのスキルに関しては以下の記事で解説しています。
【フルリモート5年目が厳選】成果を出すために必須の5つのスキルと磨き方
デメリットを大きく上回るメリット
ここまでフルリモートのデメリットばかりを解説してきましたが、もちろんデメリットを大きく上回るメリットがあるからこそ、フルリモートを望んでいる人がいりはずです。
ここでは、代表的なメリットをいくつか紹介します。
住む場所の制約がなくなる
フルリモートの最大のメリットは、働く場所を自由に選べることです。
実家に戻って親の介護をしながら働く、自然豊かな地方に移住して暮らす、海外で生活しながら仕事をするなど、人生の選択肢が大きく広がります。
「満員電車に揺られて都心に住む」という固定観念から解放され、本当に自分が住みたい場所で生活できるようになります。
住む場所に関しては以下の記事で解説しています。
【住む場所】人生にモヤモヤするなら住む場所を変えろ!幸福度を上げるためのロードマップ
通勤からの解放
満員電車でのストレスや、片道1時間以上かかる通勤時間から解放されるのは、計り知れないメリットです。
通勤時間がなくなることで、自分の時間を1日2時間以上増やせることになります。
この時間を、睡眠や趣味、勉強、家族との時間に充てることができ、生活の質が飛躍的に向上します。
通勤時間の有効活用方法に関しては以下の記事で解説しています。
【電車・車・徒歩】通勤時間が“成長のゴールデンタイム”になる!手段別・活用術
突然話しかけられたりはしない
オフィスでは、同僚から突然話しかけられたり、上司から急な仕事を振られたりすることがよくあります。
フルリモートでは、基本的に自分のペースで仕事を進められるため、作業の中断が少なくなり、集中力が高まります。
自分の作業に没頭したい人にとっては、最適な環境だと言えるでしょう。
私自身は先天性難聴という特性に加えて、集中すると周りが見えなくなるタイプです。フルリモートで働くようになってから突然話しかけられなくなったので、集中できるようになりました。
休憩時間に家事ができる
フルリモートでは、休憩時間を自由に使えるため、仕事の合間に家事や育児を行うことができます。
洗濯機を回したり、夕食の準備をしたり、子供を迎えに行ったりと、生活と仕事のバランスが取りやすくなります。
オフィス勤務ではできなかった、時間の有効活用ができるようになります。
自分のタイミングでお手洗いに行ける
オフィスでは、同僚の目が気になり、お手洗いに行くタイミングをためらってしまうこともあるかもしれません。
フルリモートでは、誰にも気兼ねすることなく、自分の好きなタイミングで席を立てます。
たったこれだけのことに聞こえるかもしれませんが、小さなストレスの積み重ねから解放されるのは、精神的なメリットが非常に大きいです。
まとめ
この記事では、フルリモート勤務のデメリットを5つご紹介しました。
- 会社への帰属意識が薄まり、一体感を得にくい
- 直接指導してもらう機会が減る
- 仕事とプライベートのオン、オフがつけにくい
- 運動不足になりやすい
- 人と交流したい欲が高まる
フルリモートは、一見するとメリットばかりに思えますが、孤独感や運動不足、オン・オフの切り替えなど、事前に知っておくべきデメリットが確かに存在します。
しかし、これらのデメリットの多くは、自分で意識的に行動したり、工夫したりすることで解決できるものです。
フルリモート勤務は、自由な働き方を手に入れるための素晴らしい選択肢です。
もしあなたが「フルリモートに挑戦してみたいけど、自分に合っているか不安」と考えているなら、この記事でご紹介したデメリットや対策、そして向いていない人の特徴を参考に、ぜひもう一度じっくりと考えてみてください。
あなたのキャリアにおいて、最善の選択ができることを願っています。
フルリモートに興味があれば、以下の記事もおすすめです。
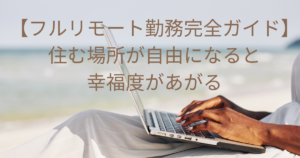
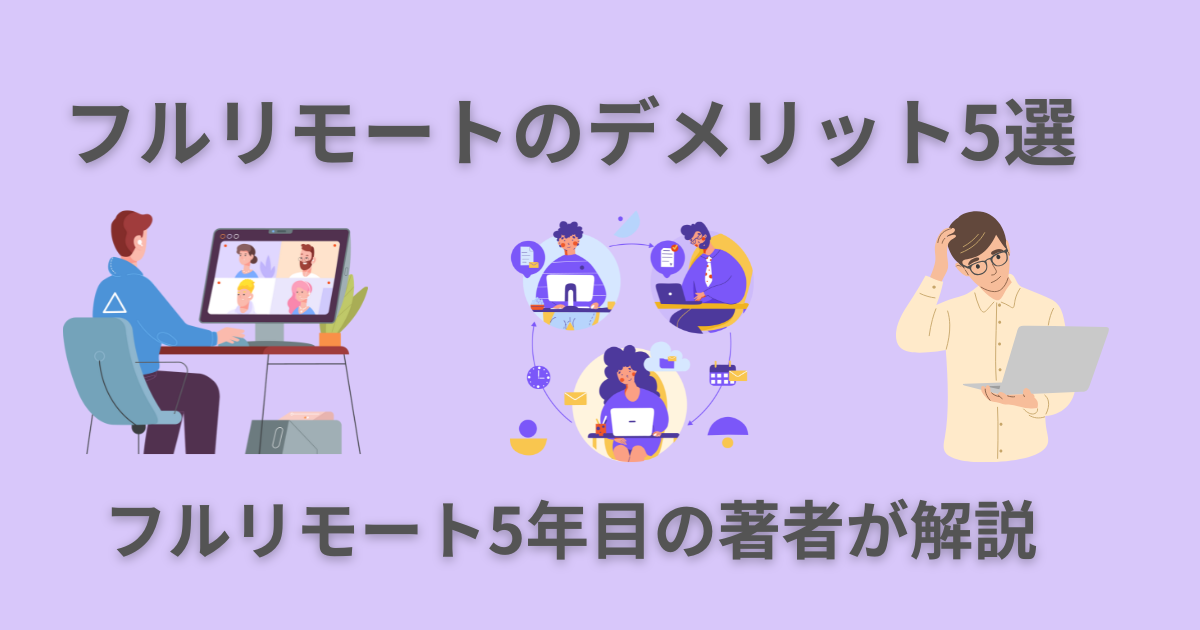
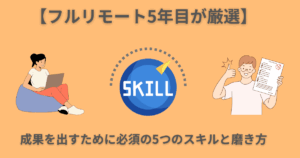
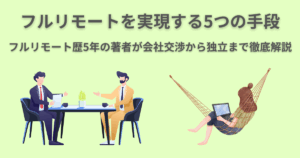

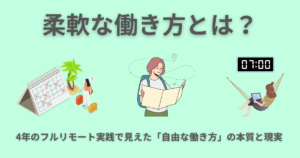
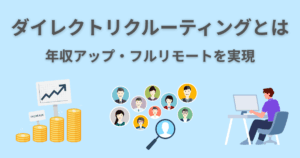
コメント